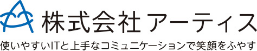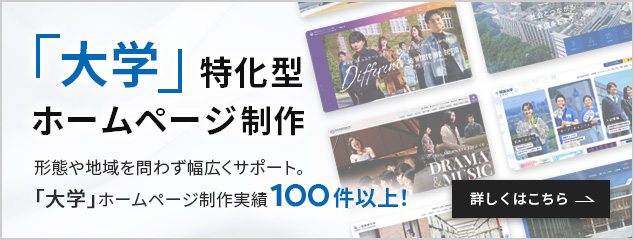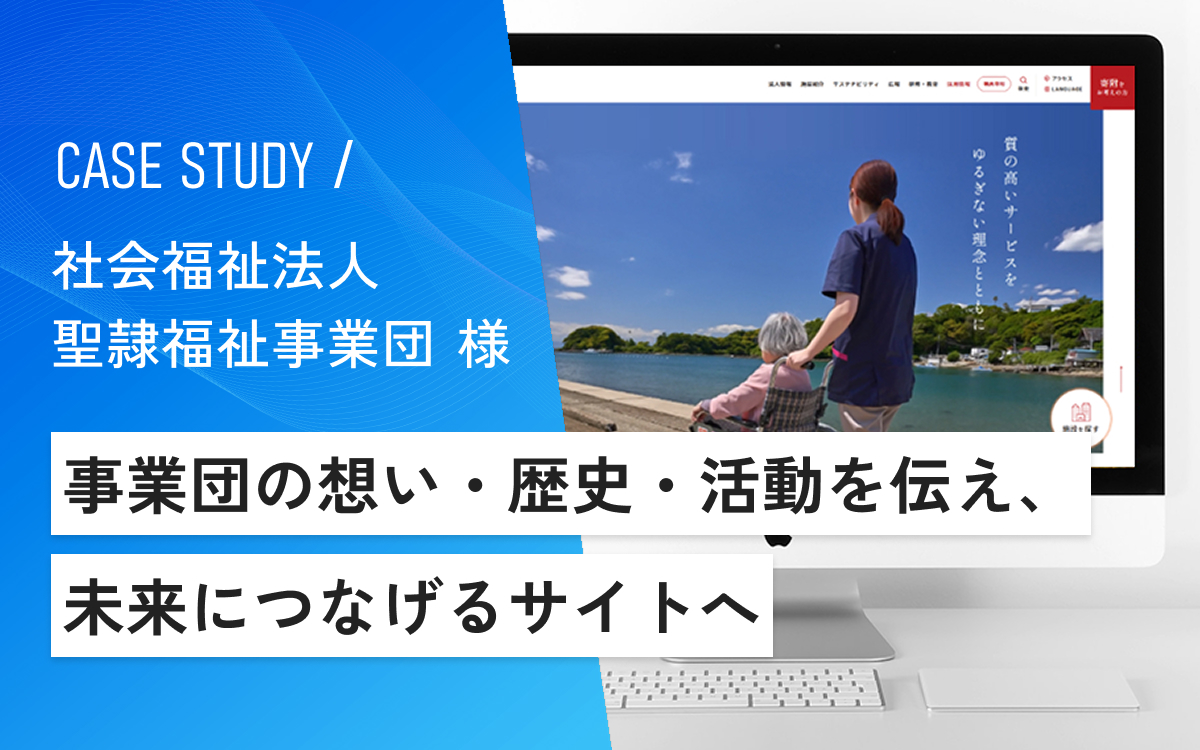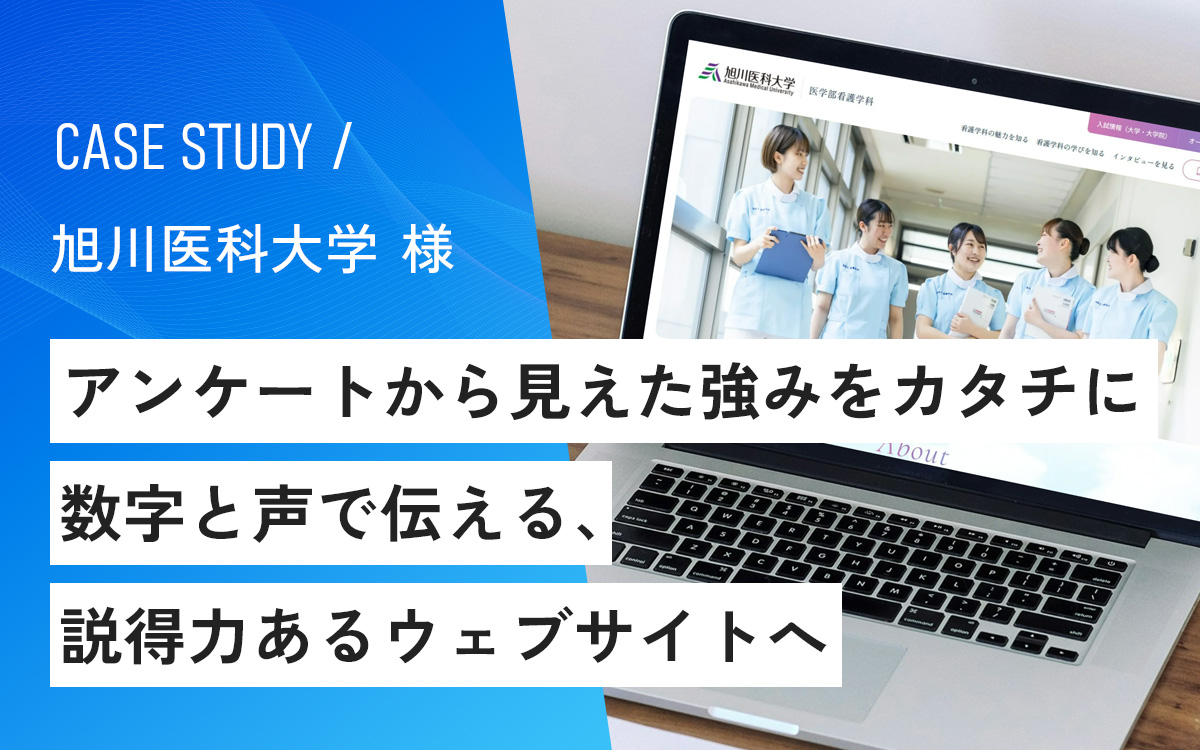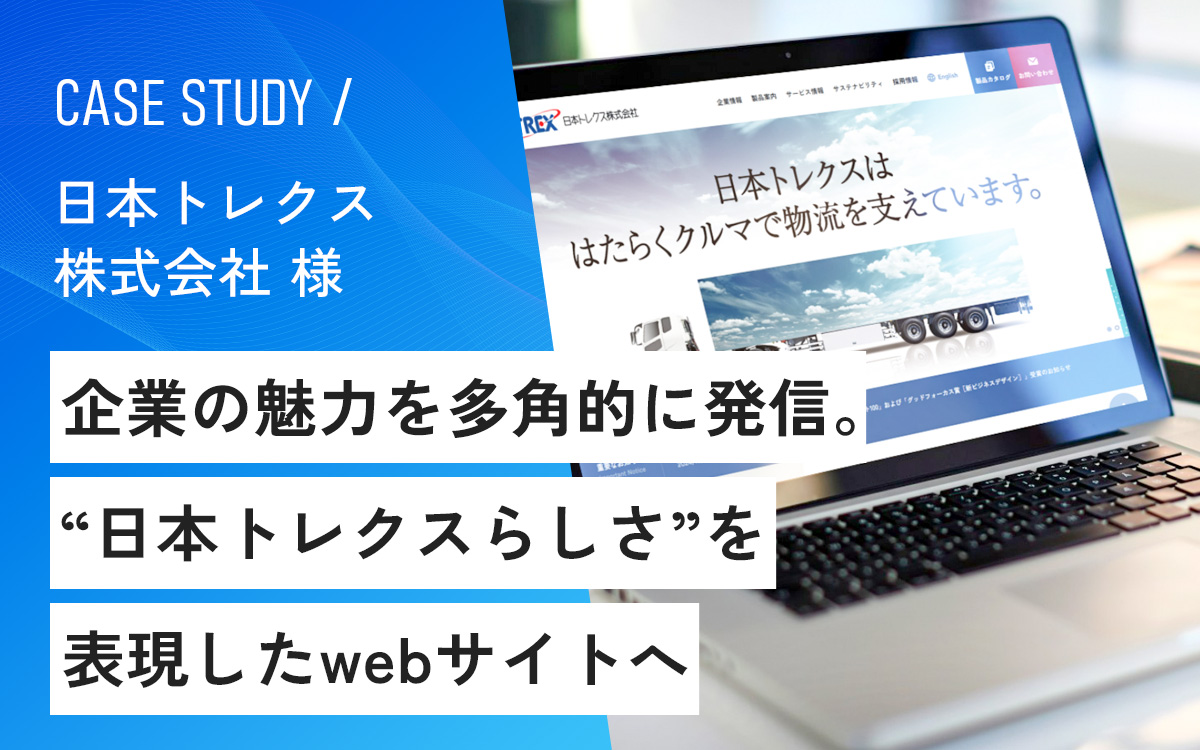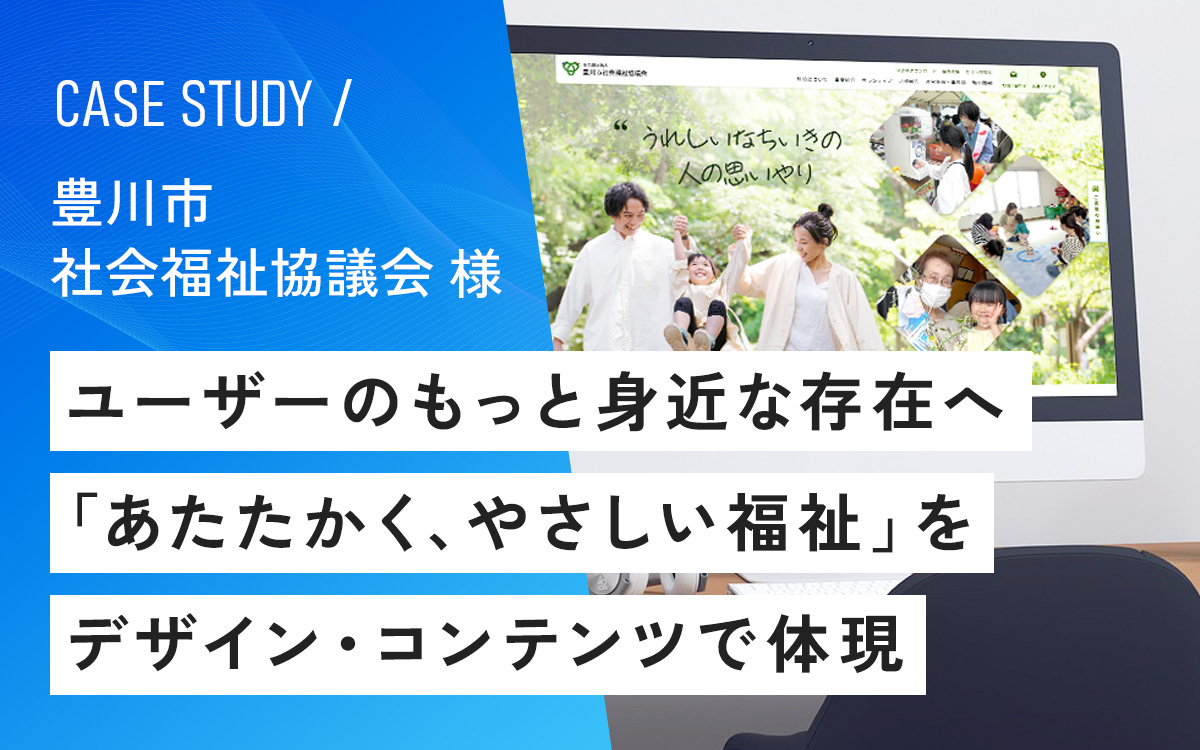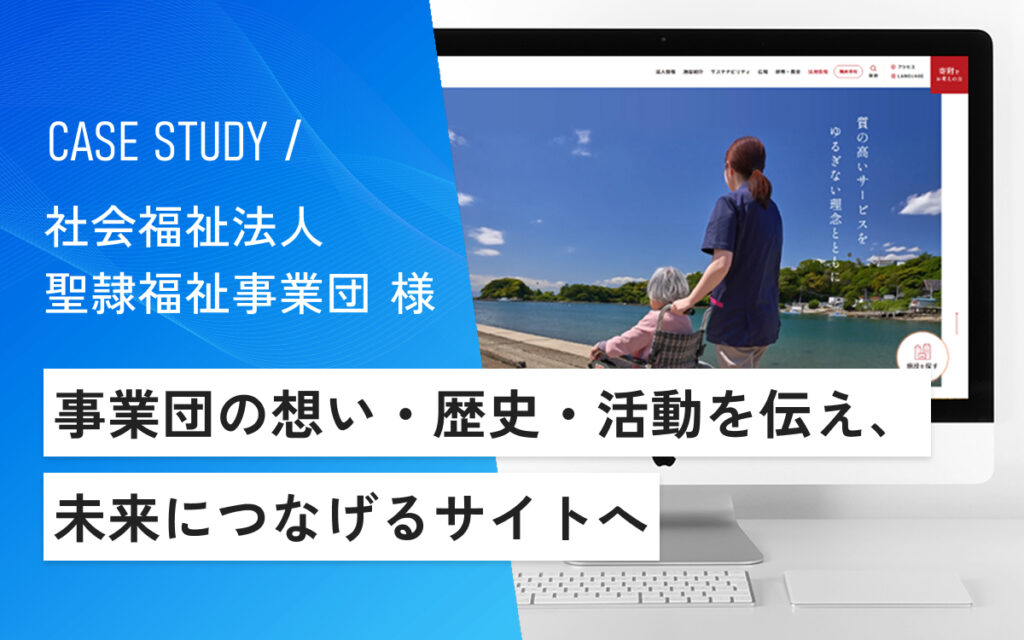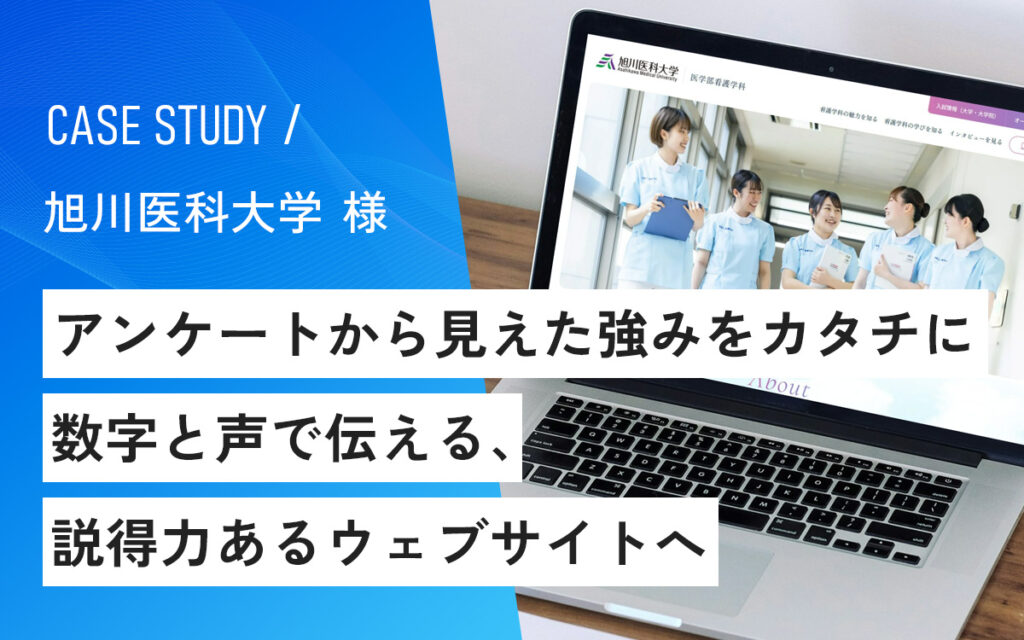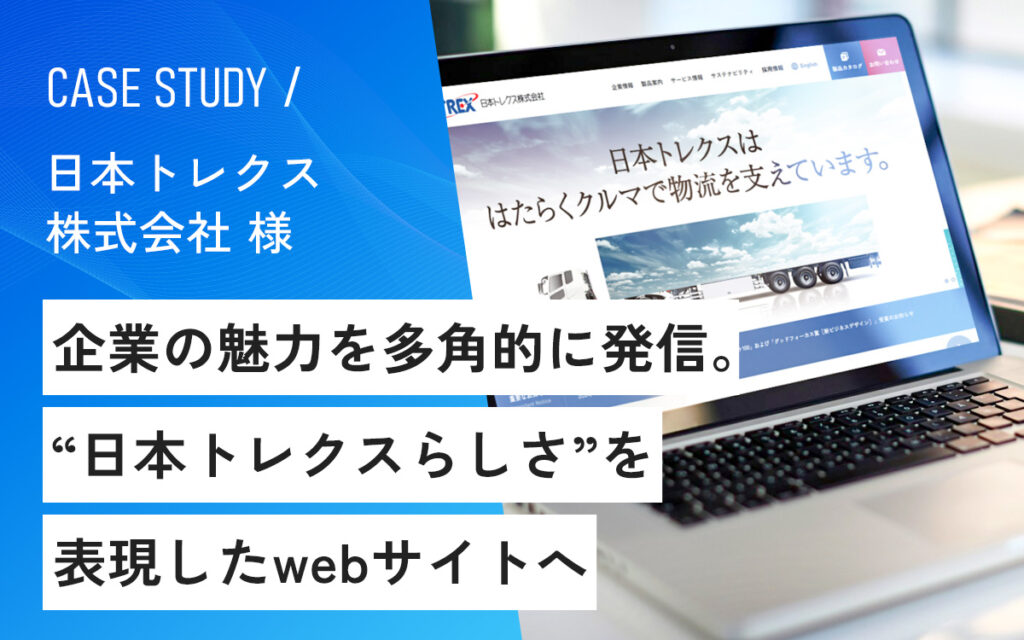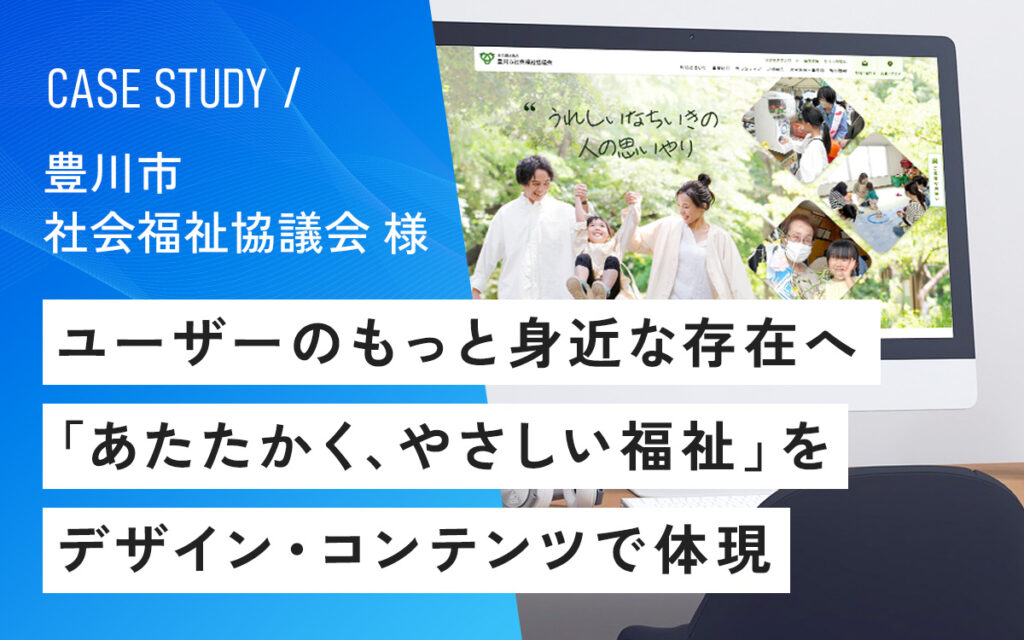【静岡県立大学様】「ウェブアクセシビリティを当たり前に」学内の意識改革を講演会でサポート

今回は、2017年から弊社と共にウェブアクセシビリティ対応に取り組んでいる静岡県立大学様にインタビューをさせていただきました。
ウェブアクセシビリティを始めたきっかけや毎年実施しているJIS X 8341-3:2016 試験の取り組み、さらに今年、学内の方々に向けて開催した講演会の経緯や講演後の反応について、詳しくお話を伺いました。

▲ウェブアクセシビリティ講演会のようす
INDEX
静岡県立大学様の紹介
静岡県立大学は、静岡県にある総合大学です。
「県民の誇りとなる価値ある大学」を目指し、学生の目線を大切にしたきめ細やかな教育と、質の高いキャンパスライフの実現に取り組んでいます。さらに、静岡県の最高学府として、独創性と国際的評価に値する研究を推進しています。
静岡県立大学 大学サイト アーティス制作実績(静岡県立大学様)
静岡県立大学様とウェブアクセシビリティの出会い
ウェブアクセシビリティの取り組みを始められたきっかけは?
本学には視覚に障がいを持った教員がおり、日常的にスクリーンリーダーを使ってサイトを見ていました。その教員から「こういうところは読み上げが難しい」「改善した方が良い」といった具体的なアドバイスをもらう機会が多かったんです。私たち自身も「もっと誰にとっても使いやすいサイトにしなければ」と強く意識するようになりました。そうした背景が、アクセシビリティ対応にしっかり取り組む大きなきっかけになったと思います。

初心に戻る、ウェブアクセシビリティ講演会
アーティスにウェブアクセシビリティ講演会を依頼された背景は?
令和6年度に改正障害者差別解消法が施行され、総務省からも注意喚起がありました。本学でも従来からアクセシビリティに配慮してきましたが、Webサイトを更新する担当者が入れ替わる中で、「なぜ必要なのか」という意図が十分に共有されていない課題がありました。
そこで、毎年実施している広報研修会の一環として、昨年度は「初心に立ち返る」ことを目的に、ウェブアクセシビリティをテーマとした講演会を開催しました。公式サイトの更新は各部署のサイト担当者がCMSを使って行っており、例えば以下のようなちょっとした工夫が必要です。
- 時間表記:「13:00」ではなく「13時」と表記する
- 画像掲載:読み上げソフトに対応するため代替テキスト※1を入れる
- レイアウト:PCやスマホなど異なる環境でも読みやすさを意識する
こうしたポイントをサイト担当者に意識してほしい、という狙いがありました。
また、サイト担当者だけでなく、それ以外の職員にも「公式サイトでどのような配慮をしているのか」を知ってもらいたいと考えました。日々の業務の中での小さな気遣いが、誰にとっても使いやすく、過ごしやすい環境づくりにつながる——そのことを改めて意識してもらうきっかけになればと思ったのです。
ウェブサイト上の画像が表示されない場合に、その画像の内容を説明するために用いられるテキストです。視覚障がいのある方がスクリーンリーダーでウェブサイトを閲覧する際に画像の内容を理解するために使われたり、検索エンジンが画像の内容を理解する手がかりとしても活用されます。
講演会に参加された皆さまの反応はいかがでしたか?
CMSで画像を入れる際には「代替テキストを入れてください」と説明していたのですが、なぜその必要があるのか、こちらもうまく説明ができていなかったと思います。
講演会で実際に読み上げソフトを使ってみて、「こうやって読み上げされるんだ」という体験をしてもらえたことで、理解がぐっと深まったと感じています。それが良かった点ですね。
講演を通して、特に心に残っている内容や印象的だったフレーズはありましたか?
「あらゆる人が平等に情報を入手するためにウェブアクセシビリティがある」という話が印象的でした。本当にその通りだなと思って、自分よがりな作り方をしてはいけないんだな、と改めて感じました。
「これは学内でもぜひ共有したい」と感じた気づきがあれば教えてください。
普段話している人が、必ずしも自分と同じように見えているとは限らない、ということを意識しなければならないなと感じました。
特に印象に残ったのは色の使い方です。文章を強調したいからといって文字色を赤字にすればよい、というわけではないんですね。太字にしたり下線を引いたりすることで伝わる場合もありますが、実際にはそれだけでは十分でないことも多く、改めて「なるほど、本当にそうだったな」と思いました。

誰もが見やすく使いやすいサイトにするための日常の工夫
CMSを使ってのウェブアクセシビリティ対応には、どのような⼯夫をされていますか︖
読み上げソフトを強く意識して作業しています。実際に、チームのメンバーが横から読み上げソフト風に読み上げて、「あ、ここはダメだ」とみんなでチェックしながら改善する、といった取り組みをしています。
学内や外部のユーザーから、アクセシビリティに関する声や反応が届いたことはありますか?
「ウェブアクセシビリティがちゃんとしていて読みやすいですね」といった声は、なかなか届かないと思います。具体的な反応を得ることは難しいのですが、視覚に障がいを持っている教員などから何も指摘がない場合は、逆にうまくできているのかもしれない、と考えています。
ウェブアクセシビリティを当たり前に
今後どのような情報発信をしていきたいとお考えですか︖
見てくださる方全員に、情報がしっかり伝わるようにしたいと考えています。
デザインをもっと凝った方が良いのでは、という意見が出ることもありますが、私たちの理想は「一目でどこに何の情報が載っているかわかる」「見たページがすっきりしていてわかりやすい」という形です。今後もこの点を意識して情報発信を進めていきたいです。
同じように取り組みを始めたいと考える教育機関や団体に向けて、アドバイスやメッセージをお願いします。
「自分が見やすい=他の人が見やすい」というわけではないことを意識することが第一歩だと思います。自分のパソコンの幅やネット環境などで見えることだけを追求するのではなく、標準的に誰にとっても見やすい状態を意識することが大事だと思います。
また、年に1回実施しているJIS X 8341-3:2016 試験もとても有効です。試験を通じて「ここはダメだったかな」と気づき、修正を繰り返すことで、次第に意識が定着していきます。そのため、最初は地道でも、繰り返し意識することが取り組みを定着させる第一歩だと思います。
私たちもまだまだ改善の途上です。いろいろな大学・企業・団体の公式サイトを参考にしながら、自分たちのサイトも改善していきたいと思っています。お互いに参考にし合いながら、ウェブアクセシビリティが当たり前の環境を作っていければと考えています。

アーティス担当者からのメッセージ
担当ディレクター 佐藤より
最初に静岡県立大学様に携わらせていただいたのは JIS X 8341-3:2016 試験のお手伝いでした。この経験は、私自身がウェブアクセシビリティの知識を深める大きなきっかけとなりました。
昨年は、ウェブアクセシビリティ講演会の講師を務めさせていただき、こちらも大変貴重な経験でした。改めて、ご依頼いただきありがとうございました。
今後もウェブアクセシビリティや、その他Webサイト更新に関することでご不明点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
株式会社アーティス ディレクター 佐藤
高校時代に1年間のメキシコ留学経験を経て、関東の大学で国際文化と多言語について学ぶ。Webディレクターとしてアーティスへ入社後は、Webユーザビリティを学びながら、大学・病院サイトを始め、コーポレートサイトのディレクション・企画業務に携わっている。
担当営業 池谷より
静岡県立大学様は2007年からお付き合いをさせていただいているクライアント様です。様々な改修、リニューアルをお任せいただくことで弊社も大きく成長することができました。
2018年のリニューアルの際には、アクセシビリティについて全盲の先生からの知見もいただき、JIS規格に準拠するだけの形式的なアクセシビリティではなく、万人にとってのユーザビリティを考えるきっかけもいただきました。
今後もより良いサイトの運営のお手伝いができるよう、スタッフ一同精一杯お手伝いをさせていただければ幸いです。
株式会社アーティス 営業担当 池谷
2015年に入社後、ソリューション事業部の企画・営業担当として、主に静岡県・愛知県内の企業・医療機関・教育機関のホームページリニューアル案件に携わる。
2025年からはアーティスCMSのプロダクトマネージャーとして開発業務を兼任している。
この記事を書いた人

- これまでご依頼をいただいたお客様にインタビューを行い、記事を作成していきます。
この執筆者の最新記事
関連記事
最新記事
FOLLOW US
最新の情報をお届けします
- facebookでフォロー
- Xでフォロー
- Feedlyでフォロー